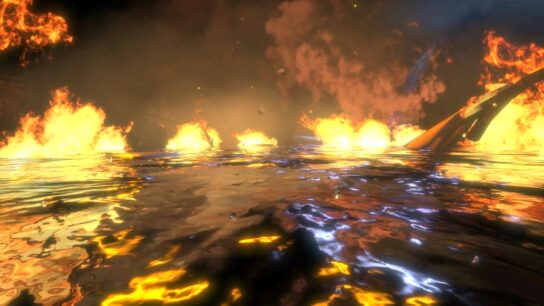最初に知ったのはGAMELIFEのレビュー記事にて。発売から16年後の2021年に現環境に適応させたVerが再リリースされたため、当時のDemoを触って以来ちょうど昔を思い出す感じで一周遊んでみた。…一番初めにGAMELIFEへのリンクを貼ってしまうと、私が書ける事柄がなにも無くなってしまうわけだが、気が付いた点を箇条書きにしていこうと思う
- 序盤こそカジュアルな雰囲気ゲームとなっているが、中盤以降はステルス要素が必要となり、終盤はパズル要素が強くなってくるので難易度はやや高め
- 主人公のスタッブスは時間経過で体力が自動回復。そのため解法を間違った場合でも時間を使ってクリアできる場合もある
- チェックポイントがこまめに置かれているのは良いが、セーブスロットが1つのため詰みセーブが起こる可能性あり。ここはかなりのユーザーから不満の声がでているはずなので修正できたのではないかと思うが

◆序盤は大量のゾンビを引き連れて多勢に無勢で人間に襲い掛かれる夢のシチュエーションを堪能できる。襲った人間は死後さらにこちらの味方になるのだから、凄まじい倍々ゲームだ。この辺りが楽しさの最高潮だという気がしなくもない

◆Qキーで敵キャラ1体を操る洗脳が行える。銃器を持った敵を狙えば射撃も可能となるので、大分楽に戦闘を行えるようになる。後半は遠距離から撃たれる機会が増えて接近が難しくなるため、なにかしらの工夫が必要だ