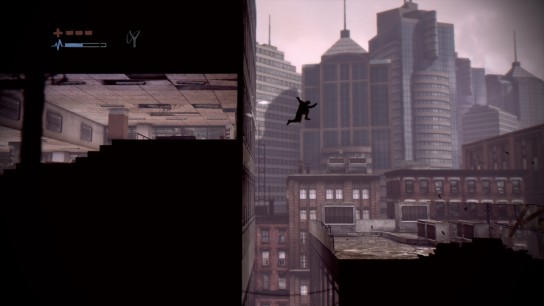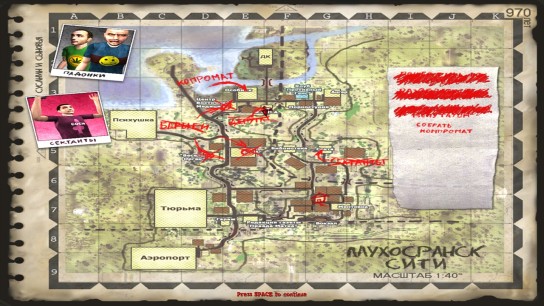コメントで教えてもらった本作を楽しくクリア。本作は1991年発売のソニック・ザ・ヘッジホッグから2010年発売のソニック カラーズまでの各ステージをリメイクし(評価が高いものを選出していると思われる)、シンプルな操作のクラシックソニックとスピード感溢れるモダンソニックの二匹を切り替えて遊ぶことができるお得感ある豪華な20周年記念作品だ。序盤、つまりメガドライブ世代の2Dステージはうまい具合に3Dに落とし込まれていて見栄えとスピード感が高いレベルで両立していて素晴らしかった。クリア後の評価が気に入らないからと、Sランクを狙いにリプレイしたくなるゲームは久しぶりだ。とにかくソニックを操作しているだけで楽しい。アクションゲームの基礎的な部分は満点に近いと言える。
が、この幸せな時間は後半から怪しくなる。Act2からはソニックアドベンチャー(1998)を始めとした3D世代をリメイクし直したステージ群を遊ぶことになるわけだが、Act1からの落差が激しくてどこかモヤモヤする。精神的に大きく変わったところは「別にBランクでもいいか」と、クリア後の評価に興味を失った点か。とはいえ、単品で見た場合のアクションゲームとしては悪くなく、2Dソニックには無い3D独自のカメラワークという最大の利点があり、ソニックの格好良い動きを追うといったキャラゲーとしての価値は高そうだ。私自身はさほどソニックシリーズに思い入れがないので、簡単に”別物”と割り切れているが…ともかく前半だけは間違いなく万人に受ける良ゲーである。

◆クラシックソニックは操作がシンプルなので事故が起こりにくい。安心安定したゲーム進行が行える

◆モダンソニックは凄まじい速度で走り回れるので爽快なのだが、操作が複雑というか、作っている側の指示に従わないとフルスピードが持続しないようなので、意外と覚えゲー要素が高い。Mapを頭に叩き込まないと簡単につまずいてスピードを落としてしまい、テンションが下がる。スクリーンショットのようなイベントシーンでは常に格好良く映るが…繰り返し遊んでくれということなのだろう